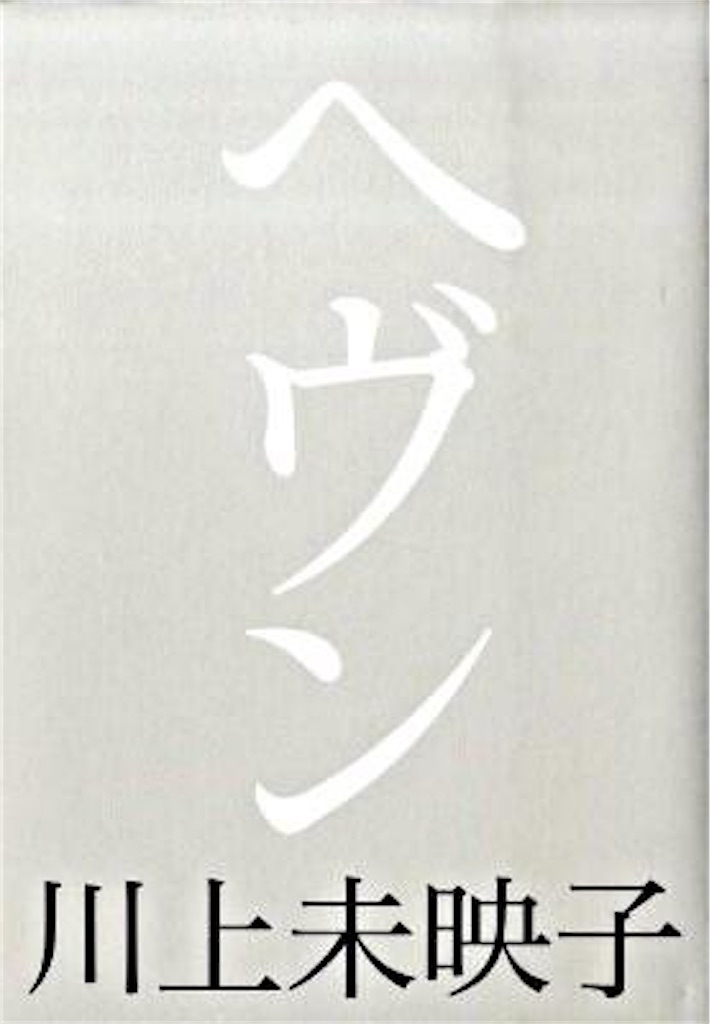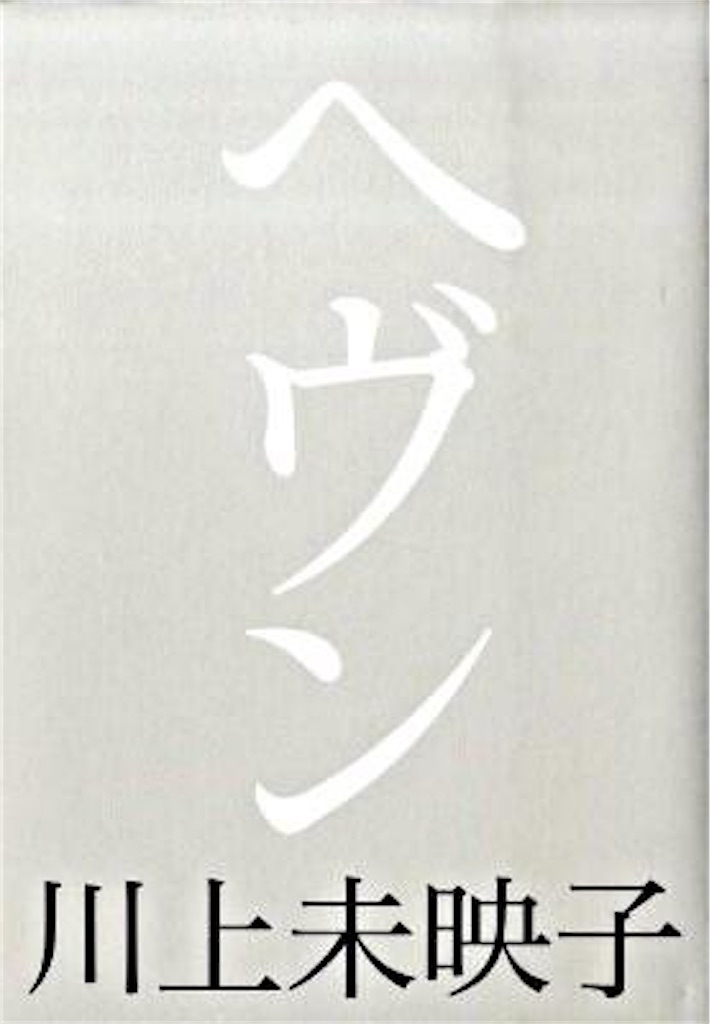
現代の作家で好きなひとを挙げろと言われたら、まず最初に川上未映子を挙げる。文体、選び取るテーマ、訴求力、ことばの美しさ、つむがれる物語、どれをとっても、たいへんうっとり、ぐさぐさ、とにかくもう大好きなのである。そんななかでも「ヘヴン」、この作品がめちゃくちゃ好きだ。
※ネタバレ含みますので未読のかたはご注意ください。また、文体に合わせてお名前は敬称略とさせていただきました。
今までと違ったかたちから、今までのかたちへ新しく
「ヘヴン」を読む前から
川上未映子が好きだった。はじめて彼女の作品に触れたのは「わたくし率 イン 歯ー、または世界」、それから「先端で、さすわさされるわそらええわ」、そして「乳と卵」。まずタイトル
からしてしびれる。「先端で~」は最近
筑摩書房より文庫化され、サイン本を入手しとてもうれしい!
先端で~は詩集だけど、「小説ってこんなふうにも書けるんだ」と読んだときは相当な衝撃を受けた。なんだかとにかく自由。文章に意思があるみたいな、踊っているみたいな、「ひ、ひとってこんな文章を生み出すことができるのか」という感動。前者二作は正直に言うと話の内容はほとんどわからなかった。でもどっぷりと惹かれた。意味を完全に汲み取ることができなくても夢中になれる文章って本当にすごいと思う。
芥川賞を受賞した「乳と卵」もまたこれ独創的で、大阪出身の姉妹(主人公は妹)と、姉の娘のある夏を描いたものなんだけど、
大阪弁でつづられている。ご本人も大阪出身とのことで、よどみなく
大阪弁で話が進んでいく。これがまたリズミカルで読んでいて心底いいきもち(後に出版される、同じ主人公である「夏物語」も、いずれ感想を書きたい……21年9月追記書きました→
夏物語/川上未映子)。
もう一作、「そら頭はでかいです、世界がすこんと入ります」という随筆集があり、そのどれもに惚れ惚れ惚れ惚れする! とにかく読んでいてこころが動かされる文章なんである。そんなふうにザ・川上ワールドに浸っているなか新しく出た「ヘヴン」。
初の長編小説ということで手に取らない理由がない、読んでみると「
大阪弁じゃない、わたくし率みたいなテンポじゃない」というのが最初の印象だった。がっかりしたわけじゃない。言ってしまえば「ヘヴン」は(それまでの
川上未映子の作品と比べると)型通りの小説のかたちだった。だけど、それはなによりも新しいかたちに思えた。そして、その新しさにふれられたことがとにかくうれしかった。
「僕」と「コジマ」
『ヘヴン』(川上 未映子):講談社文庫|講談社BOOK倶楽部
<わたしたちは仲間です>――十四歳のある日、同級生からの苛めに耐える<僕>は、差出人不明の手紙を受け取る。苛められる者同士が育んだ密やかで無垢な関係はしかし、奇妙に変容していく。葛藤の末に選んだ世界で、僕が見たものとは。善悪や強弱といった価値観の根源を問い、圧倒的な反響を得た著者の新境地。
主人公は十四歳の男の子。一度も名前が出てこないので、「僕」と表記。「僕」は斜視であり、同級生から「ロンパリ」と呼ばれひどい苛めを受けている。「僕」のもとへ届く手紙、差出人はクラスメイトのコジマという女の子だった。コジマもまた、教室内で苛めを受けている。コジマは身なりを汚くしていて、それが原因で苛めを受けることになるのだけど、その汚さは彼女にとって大事なものだった。「僕」の斜視、コジマの「汚さ」、それが「しるし」なのだとコジマは語る。「僕」もコジマも、教室内では言葉を交わさない。自分が苛められているときは、なるべく自分を見ないでほしいと思う。相手が苛められているときは、もどかしい気持ちになる。「友達になってほしい」というコジマの申し出から、二人は手紙のやりとりをして距離を縮めていくけれど、教室ではまるで他人のようなふりをする。でも二人で会っているときは、友達の会話をする。すごく等身大。うれぱみん(うれしいときに出る
ドーパミン)、こにゃにゃちは、いっちょらい(一張羅のこと)……。そういう、かわいい言葉をつかったりもする。
普段、クラスメイトからひどい理不尽を受けているコジマは、「僕」と話しているときや手紙のなかでとても楽しそうにしている。その対比がつらい。
なぜコジマは「僕」に手紙を出したのか、「僕」と友達になろうと思ったのか。それは自分と「同じ」だから。苛められていること、「僕」の目が「しるし」であること、自分たちが強いからこそ現状を受け入れているのだということ、互いのしるしのおかげで自分たちが出会えたこと。そのどれもがコジマにとっては本当に大切なことで、意味のあること。だけど「僕」とコジマの考え方は少し違っている。たとえばコジマが「私たちはなぜ苛めに抵抗しないのだと思うか」と「僕」に問う場面がある。「僕」は「僕が弱いからだと思う」と答える。わたしは、ここで答えが出てしまったのだと思った。コジマは「僕」が言ったことをすぐに否定して、「受け入れているのは私たちが強いから」ということを言う。
どちらが正しいとか間違いとか、僕とコジマにおいてはそういったことを考えるのは不毛で、ただ、互いを仲間だと認識して、コジマのことをどんどん知っていくこともできて、「僕」もコジマのことをとても大切に思っていて、なのに、二人の考えが少しずつずれていっていることが、本当につらかった。
「僕」と「斜視」
「僕」が苛められる原因は斜視にある。ただそれはあくまで「僕」が思っていることであって、「僕」を苛めている側は、もはや「斜視だから苛めている」という意識はない。
苛めの主犯は二ノ宮(クラスのリーダー的な存在)、その取り巻き、そして二ノ宮と対等でありながら直接的な苛めはせず、傍観にまわる百瀬という人物。主にひどいこと(チョークを食べさせる、掃除用具のロッカーに入れと言う、殴る、蹴る、など)をするのは二ノ宮だった。
あきらかに悪は二ノ宮で、「僕」はなにも悪くない。そしてコジマはそんな「僕」のことを正しいと言う。「僕」にとって、苛めの原因である斜視を、すきだと言う。わたしはコジマのことが好きだけど、「僕」のことも好きだから、なにを思えばいいのかわからなかった。
「僕」にとって、暴力は二つあったのだとわたしは解釈している。ひとつは直接的な暴力。二ノ宮たちから受ける理不尽。もう一つは、コジマの強さ。コジマは、耐え抜こうとする強さを持とうとしていて、それを「僕」にも共有しようとする。「僕」にとってコジマは唯一の味方で、友達で、裏切れない人だから、「僕」はコジマの意思を受け入れようとしたのだと思う。コジマも、「僕」自身のために強くあろうとしている。
だけど二人は結局別々のほうを見ることになる。こういうことを考えると、この斜視の設定、ロンパリという言葉が、かなり重くのしかかってくる。そのしるし自体に、本当は意味がないのだとしても。
コジマは「僕」を丸ごと受け入れてくれる。周りから忌み嫌われる斜視のことをすきだと言ってくれる。ただみんな、その目をこわがっているだけなのだと、その目は僕自身なのだと一生懸命伝えようとしてくれる。
だけど「僕」は、納得できていない。自分を苦しめている斜視を、すきになれない。すきになろうともしたのだと思う。だけどコジマが言ってくれた言葉を思い返して無理やり言い聞かせているような印象があって、そのすれ違いみたいなものがひたすらしんどい。
「僕」と「百瀬」、「百瀬」と「コジマ」
物語上、いちばんおそろしいのは百瀬だ。百瀬は正直に言うと、「僕」にまったく興味がない。「僕」を取り巻いている苛めのあれこれにも、興味がない。二ノ宮たちが楽しそうに「僕」を苛めているのをとても近くで眺めている。だけど興味がなくても二ノ宮たちと行動するから、いやでも「僕」の視界に入る。
「僕」と百瀬が二人で対峙する場面がある。「僕」が偶然百瀬を学校の外で見つけて「話があるんだよ」と、話があったわけでもないのにそう話しかけ、そこから二人の会話が始まる。
「僕」は百瀬に救いを求めてしまったのだろうなと思う。百瀬だけは「僕」に直接的な暴力をふるわなかったから、百瀬に「苛めをやめてほしい」と言ったら二ノ宮たちに伝えてくれるんじゃないかって、そういうことを「僕」は考えていたのではないか。たとえばそんなことを無意識下で考えていたとしたら、「僕」はコジマの考えとは別の世界に踏み出そうとしているということだし、でもそれは決して間違いではないし、そこで相当しんどくなっているのだけど、さらにしんどいのが百瀬の言い分だった。
あくまで中学生という子どもっぽい言い分と、哲学的な主張を交えた、おそらくこの物語のなかでいちばん確固とした持論だった。コジマがいつも「僕」に伝えてきたことも、確固たるものではあるのだけど、でもどこかで「自分に言い聞かせている」感があって、少し脆さもあった。
対して百瀬は自分たちがしていることになんの疑問も持っていなくて、百瀬にとっては「たまたま」で「めぐり合わせ」で「斜視は関係なく」て「したいことをしている」だけで「意味のないこと」だった。
「僕」が百瀬に「自分が同じことをされたら、自分の身内が同じようなことをされたら苦しくないのか」と訊くと「苦しいに決まっている」と、百瀬は言う。でも、それと「僕」の苛めはまったく関係がないとする。「自分がされたら嫌なことは他人にしてはいけません」というのはインチキだと、屁理屈に聞こえるけど、けれどインチキだと思う理由を百瀬は述べる。
それでもどうしてコジマよりも、百瀬の言い分のほうが正しく感じてしまうのだろう。それはすごくこわいことだった。コジマと百瀬は、言うなれば正反対のことを言っている。コジマは「すべて意味のあること」とする。百瀬は「すべて意味のないこと」とする。
「僕」にとって、どちらの言い分を信じれば楽になるのか、それを考えたときに後者だと思ってしまったから、わたしは百瀬を正しく感じてしまったのだと思う。
誰かを殴ったり蹴ったりできる人間がいるのに、「君はどうしてそれをしたくないんだ? できないんだ?」と百瀬が「僕」に問いかける。だけどそれはやっぱりコジマとは正反対だった。コジマは「今を受け入れている」自分たちが強いと思っているから。
「ヘヴン」
タイトルでもある「ヘヴン」。これは、ある絵に対してコジマが名付けたものだ。なんの絵なのかは作中では明記されていないけど、
シャガールの「誕生日」なのではないかと考察されている。
【作品解説】マルク・シャガール「誕生日」 - Artpedia アートペディア/ 近現代美術の百科事典・データベース
「(前略)ふたりが乗り越えてたどりついた、なんでもないように見えるあの部屋がじつはヘヴンなの」
「僕」とコジマが美術館へ「ヘヴン」を見にいく場面で、コジマがヘヴンの説明をするセリフ。だけど二人は結局ヘヴンへたどり着けない。コジマの体調が悪くなってしまって、一番奥にあったはずのヘヴンを見る前に、美術館から帰ることになる。
「ヘヴン」は探すものではない。コジマが言うように、たどりついた場所がヘヴンなのだと思う。けれど百瀬はこんなことも言っていた。
「地獄があるとしたらここだし、天国があるとしたらそれもここだよ」
乗り越えないといけない場所にヘヴンがあるのか、誰だって、どこにいたって、「そこ」をヘヴンにできるのか。コジマと一緒にいる場所がヘヴンだったのかもしれないし、そうじゃなかったのかもしれない。そして終盤にかけて「僕」とコジマにとって本当に本当にかなしいことが起こり、状況が変わっていく。「僕」とコジマが二人で会っていたことがクラスメイトに知られ、「僕」とコジマが公園で手に触れあっているときに「つづきやれよ」と二ノ宮たちに揶揄される。「なまでみたことないから、ここでセックスしてみせろ」と言う。
「僕」は抵抗する、今まで受け入れることしかできなかったのに、コジマのために、コジマだけは帰してくれと立ち向かう。だけど圧倒的な暴力の前ではとても無力だった。「僕」は落ちていた石を持って、それを二ノ宮たちに投げつけることも考えた。けれど結局、やろうと思えばできるかもしれなかったことを、「僕」はできなかった。だけどそれはコジマがすきだと言った「僕」だった。そして百瀬に「どうしてできないんだ」と疑問視された「僕」だった。
最終的に服を脱がされかけたコジマが二ノ宮の前に立ってほほえみ、二ノ宮の思考を停止させる。それは「僕」が見たことのないコジマだった。一同が動けないでいるときに、通行人に見つかりクラスメイトたちは逃げてゆく。そこから「僕」は、コジマと離れた。「僕」にとって大切な友達のコジマと離れることになった。
それから「僕」は斜視の手術を受けることを決める。ここには書ききれなかったけど、「僕」と母親の関係性も脆くてけれど強いつながりがある。斜視の手術はとても簡単(といわれている)、費用だってたったの一万五千円。どうしてそれを今までできなかったのか、どうしてできるようになったのか。今まで話してこなかった苛めのことを母親に打ち明けた「僕」に、できることが増えたのだと思う。
「僕」は自分なりの答えを見つけることができたんだろう。斜視の手術が終わり、目を開けたとき、視界に映ったのはとても美しい景色だ。それこそそこは「ヘヴン」だったのかもしれない。だけどそこがヘヴンなら、ただつらいことだった。あんな絶望の描き方はほかにない。「僕」が見た景色は、ただの美しさ。コジマ、しるし、自分を取り巻いていたもの、失ったもの、得たもの。だけどその美しさが「僕」にとっての救いになってほしいと願わずにはいられない。「僕」は本当は、すべて意味のあるものにしたかったのだと思う。コジマを信じたかったのだと思う。
川上未映子作品を読んでいると、いろんなキーワードが出てくる。そのキーワードを読み解いたりしているのがこちらのムック。このムックも最高によかったので何作か読んで「いい……」となったのならこちらもぜひ読んでほしい!
川上未映子 :河出書房新社編集部|河出書房新社
彼女の作品をいくつか読んでいると、「本当のこと」という言葉がよく出てくる。その「本当」が指す意味は作品によって違うのかもしれないけど、ヘヴンでは百瀬のセリフで、「弱いやつらは本当のことには耐えられないんだよ。苦しみとか悲しみとかに(後略)」と出てきた。
本当のことってなんだろうと、川上未映子の作品を読んでいるといつも思う。人間の奥底にある、繕わない、誰の意見も関係のない、「本当に自分が思っていること」なんだろうか。ただそれを見つけるのはとても難しくて(自分自身のことなのに)、仮に見つけられたとして発信できるのかという疑問もあって、そしてそれを「本当のこと」だと思ってもらえることはあまりにも少なくて、「本当のこと」って本当に存在するのか。
ただ、ヘヴンのなかで「本当のこと」を言っているのは二人いるのだと思う。コジマと百瀬。正反対だと書いたけれど、ひとつだけ共通点があるのなら「本当のこと」を言っている、伝えようとしているところだ。
いつもそうなのだけど、ヘヴンを読むと本当にしんどくなる。心臓が痛い。視界がぐらぐらする。内臓が圧縮された感じになる。だけど何度も読んでるし、これからも何度も読むんだろう。何度読んでも結末は変わらなくて、だからこそ最初の十ページですでに涙が出てきたりするんだけど、十年前に読んだときとは少しずつ自分の思うことも変わってきている気がするので、読むたびに「本当のこと」に近づいてゆきたいと思う。
mrsk-ntk.hatenablog.com